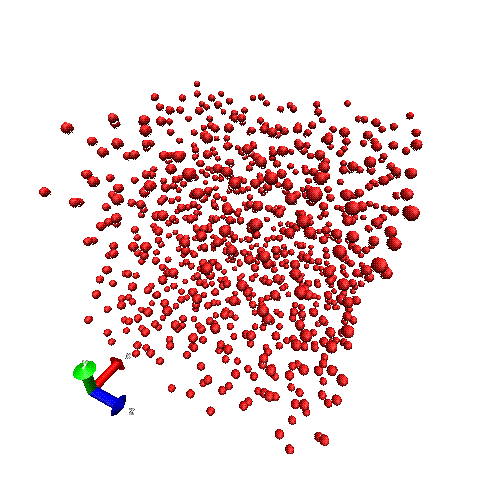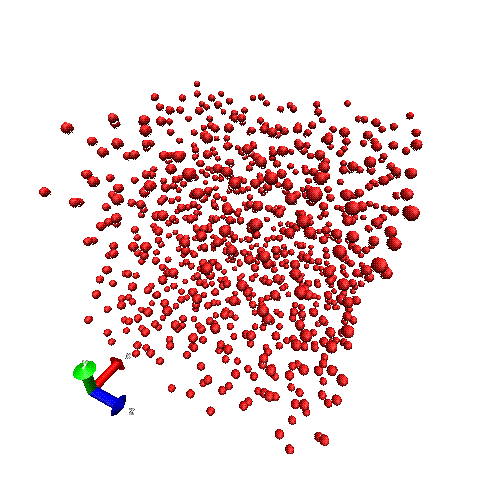
LJ-liquid MD simulation
3回生の研究室訪問はいろんな研究室を巡る最後のチャンス。
各研究室のことを知るだけではなく、いろんな分野の研究室があり
今の化学(科学)の流れが見えてくるかもしれないので、
いろいろ回ってみるのもいいかもね。
------------------
メッセージといっても大上段に構えて
言いたいことは特にないので、
個人的な体験でも書かせて頂きます。
福井県の出身で、高校ではサッカーまじめに!?やってました。
共通一次(社会2科目はしんどかった)第一世代ということで
京大・工・工業化学科(当時は入試から6専攻別々であった。)
はを受けましたが、なんと大学入試が定員割れ。
で、その後ことあるごとに工化の教授陣から
「君らは工化始まって以来最低だ」とか言われ続けましたね。
その意味で、授業で先生が「おまえらは。。↓↓(thumb down)。。だ。」とかいうのは
20年前から言われてるんですね。(笑)
[注:工学部御三家(工化,機械,電気)が昔は医学部より難しかったのは事実らしい。
電気の先生の定年退官講演で,当時の蛍雪時代(しらんやろね)をスライドにしてみせてくれた。
医学部の教授を高校の同級生にもつ某工化の先生の話(又聞きですが)では,
その医学部教授いわく。「おれはおまえより成績が悪くて医学部にいった。
その後医学部が超難関になって喜んでると思うかもしれんけども,苦労もしてるんだ,
お前がうらやましい。 医学部では,小生意気な学生が我々にきびしい質問を授業で
なげかけてきてしんどいが,工化では学生のレベルダウンでそんな苦労しなくても
いいんだろう。」だとさ。]
「授業に行くやつは??だ。自分で勉強しないと意味ない。」
という体育会の先輩の言葉の前半だけを忠実に守って
大学の最初の2年間無為にすごしました。でも、今振り返って
あの暇な時代(ただしお金はなかったね。今は、お金も時間もない。!!)
が一番貴重な学びや遊びや体験ができたようにも思います。
今と違って当時は単位はほぼ全員が3回生でそろったし留年も4年まではなし。
(土曜も授業あったし、土曜の3こまめも授業あった。実験は月から金までびっしり。
学力低下とか言われてますが、授業や実験の時間が減っていれば当たり前ですよね。)
有□化学も3回生で早々にドロップアウトしたので、
いちばん化学から遠ざかっている研究室に行こうと決めてました。
それ以来、宇治の原エネ(現エネルギー理工研)に15年ほどお世話になりました。
宇治での、思い出はなんといってもセミナーですね。丸一日、本や論文読むんですけど
式とか全部ホワイトボードでその場で導入するんです。4回生の時は、ほんとに
何が書いてあるのか、何を皆さん議論してはるのかを全くわかなかったですね。(笑)
記号の下に添え字が3つとか、4つついているとかなんじゃこれって(笑)
[でも、何年か経つとG. D. Mahan ”Many-Particle Physics"を輪読して
Feynman diagramどうのこうの議論してしまうんだから、
そのとき教えて頂いた先生方にはとても感謝してます。]
今は授業でもわかりやすいように、懇切丁寧に教えてるつもりですが、
全く理解できないことを経験して、その距離感を埋めようと
自分で勉強していくってことも大事かもしれないですね。
人に教えてもらってもその時はわかったつもろでも実は身に付いてないしね。
そういう意味で、研究室ではテーマを自分自身で掘り下げていってほしいですね。
---------------
垣内研は、「界面」というキーワードのもとに
バイオから、電気化学、表面界面化学、fsレーザーを用いた非線形分光、
理論計算(第一原理からシミュレーション)まで、ものすごく幅の広いことをやってます。
ただし、ただ幅広いだけではなく、得られた実験結果を
物理化学を用いて解析するという方向に深めていっており
それが当研究室の特徴であるように思えます。
---------------
友人、親、親戚 「いまどんな研究やってるの?」
学生 「 。。。むにゃむにゃ。。。」
友人、親、親戚 「で、それが何の役にたつの?」
学生 「。。。むにゃむにゃ。。。」
友人、親、親戚 「へーえ。むずかしいことやってはるんやね。」
学生 「(だったら、聞くなって。心のなかで思いながら)
いえいえ、大したことやってないんで。」
というのがこれまでのパターンでしたが、これらの問いに如何に答えるか。
研究室でテーマ与えられたときには必ずしも答えが決まってるわけではないので
自分自身で掘り下げていってほしいですね。
------追記---------
教養で数学教えていた森 毅のおっさんもたまには良いこと言ってます。
(採点は階段から答案用紙を放ったとか、カレーの作り方で通ったという噂があるが
容赦なく落とすしたんだな、おっちゃんは。)
以下コメント(カッコ内)を加筆して紹介します。
朝日新聞 2003年12月17日の記事より
....
「 学びは人間関係の中に成立する。」 (そう思う。)
..
「賢(かしこ)に教わるぐらいアホでもできるわ、
アホから教わるのがほんまの賢や。」....
.......(ホンマニ解っている人はアホになれるんやろね。
熱力とか電子移動の→とか今でもよく理解できてないんだけど。。。誰に教わる?)
....
教官がいい加減だと、学生は努力せざるを得ないでしょう。
(これは昔の話のような。教官がいい加減というのはいつの時代も同じかも。)
研究室に活気が生まれて、教官も学生も自然に賢くなっていくんです。
こういう賢くなりうる関係が理想的な学び方ではないでしょうか。
(ありがたいことに、こういう人がたまにいますね。教師冥利につきるっていうんでしょうか。)
...
学力低下が社会問題になってますが、本当に大事なのは、
学力がなくとも
何とかする力をいかに育てるかです。 (なんとかする時にしか、学力はつかないような。)
難しくて分からない問題も「こりゃ面白いわ」と思えば突破口が
見つかるかも知れないのに,
「分からないといけないから」と、
大人がやさしく説明してしまう。
(やさしくというか、自分の持ってる引き出しから説明してしまうのかも。
それがヤバイ時もあるように思えます。)
ムリやムダを省いて答えを出そうという、効率主義の教育ではだめ。
(実験装置自作してプログラム一から書いてどうのこうのって最近しないわね。
結構楽しいんだけどね。....データはなかなかでてこないのは事実なので。)
...
分からんことを楽しむのも、立派な能力です。........
(楽しむということばより「分からんことで遊ぶ」というのが近いような。)
----追記2-----
あのアントニオ猪木大先生も
「バカになれ。夢を持て。」
というジャンパーを最近(2004年1月)着ておられるようだ。
----ということで。
どこの研究室いってもある意味”入れ込ん”だら
(これをM1の時の相転移と呼ぶ人もいる)おもろいんちゃうかなと。
----さらに言えば、
成績順で配属研究室が決まる今のシステムは、ちと好かないですね。
優の数が多いオールラウンドプレイヤーって「どうなん」というとこもあるし、
現役の先生でも学部生時代はまったく学校にきてなかったって
言う人が結構多いけどね。(笑)
------------------------------------------
-------- 備忘録:最近読んだ本 ------------
------------------------------------------
全く関係ないかもしれないが、ムーアの法則でもおなじみ
ゴードン・ムーアGordon
E. Mooreインテルの共同設立者インテル社名誉会長
は、大学・大学院で”化学”を専攻していた。
NO2の赤外分光による構造決定が学位論文のようだ。
卒業後、半導体研究のスタートを切ったショックレー研究所で
一番役だったのは”ガラス細工”だったと本で述べている。
”インテルとともに」私の半導体人生 ゴードン・ムーア
玉置直司取材・構成 日本経済新聞社”
-----------
科学を学ぶと言うこ
と 大野克嗣 岩
波書店‘科学’ 巻頭言・2000年10月号より一部抜粋
----------------------------------
内田 樹(タツル) 「おじさん的思考」 晶文社 2002
より 抜粋(ごめんなさいあまりにもおもしろいので,著作権をviolateしてるとおもいますが。さて,工化の皆様の反論は?)
大学全入時代にむけて
ある予備校の資料によると、はやけれぱ二〇〇八年に、「大学入学志望老数」と「大学定員」が同じになる。これはどういうことかと言うと、その年には「どこ
そこの大学でなきゃ、やだ」というわがままさえ言わなけれぼ、受験生全員がめでたく大学生になれる、という「大学全入時代」が到来するということである。
大学全入。それがどういう事態を意味するのか、ちょっと考えてみたい。
(中略)
すでに現在の平均的な大学一年生の学力の水準は(予備校関係者と大学関係者の証言を信じるならば)三〇年前の中学三年生のレベルにまで落ちている。この恐
るべき事実が「偏差値」という指標の詐術のせいで前景化していないだけのことである。
ご存知のように「偏差値」というのは、その人が、ある同年齢集団の何番目あたりにいるかという相対的な「位置」の指標であって、「学力」の指標ではない。
同年齢集団全体がレベルダウンした場合、偏差値からは学力の低下という事実は知ることが出来ない。
さいわい予備校は毎年同じような難度の模試の問題を出題しているので、素点の比較によって学年ごとの学力を比較することができる。その結論が「一年間で一
点のペースで平均点が下がっているという事実である。一〇年で一〇点、三〇年で三〇点。いまどきの大学生がバカに見えるのは,決して私たちの幻覚ではな
く、じじつ大学生がどんどんバカになっているからなのである。
(中略)
「大学全入」によって、二一世紀の大学は現在の高校と同じレベルの教育機関にたる。それはそれで仕方のないことである。しかし杜会の運営には、一定数の知
的エリートがやはり必要である。大学が「高校」になってしまったら、「大学」に対応する教育機関が必要となる。これは論理的に自明のことである。
新基準での「大学」に該当するのは、東大をはじめとする一握りの超難関大学と欧米の大学だけであろう。それ以外の大学では、「大学」としての最低限の教育
水準を保つためにも、出来の良い学生には大学に残って修士号を取得することが薦められるようになるだろう。
つまり二一世紀のはやい時期には、「一握りの超難関校+欧米の大学+ふつうの大学の大学院」が現在までの「大学」に相当するようになる。この三つのカテゴ
リーの定員の総和が大学志願者数の数%で収まれぱ、だいたい昭和初年の大学進学率ととんとんになる勘定である。
つまり「大学(という看板を出した学校)にゆくのが簡単な時代」とは、「大学(に相当する学校)を出るのがすごく難しくなる時代」なのである。
(中略)
最近の調査によると、小学校六年生の段階ですでに算数の授業を理解できなくなってしまった小学生が過半数を超えている。分数のわり算くらいのところで学校
の授業が分からなくなってしまって,授業を聞くのを止めてしまうのである。
授業を聞くのを止めてしまうというのは、とても深刻なことだ。知識が身につかないからではない。「ものを習う」ための基本的なルールが身につかないからで
ある。
「ものを習う」というのは、「知っている人問」から「やり方」の説明を聞き、それを自分なりに受け容れ、与えられた課題に応用してみて、うまくいかないと
きはどこが違っていたのかを指摘してもらう、という対話的、双方向的なコミュニケーションを行うという、ただそれだけのことである。しかし、このコミュ
ニヶーションの訓練を通じて、子どもたちは「説明を聞くときは黙って、注意深く耳を傾ける」「あとで思い出せるように(ノートなどの補助手段を使って)記
憶する」「質問は正確かつ簡潔に行う」「集中している人の邪魔をしない」などという基本的たマナーを自然に身につけてゆくのである。
しかし、小学校の段階で「ものを習う」ことを放棄し、「ものを習う」仕方そのものを身につけずに大きくなってしまった子どもは、長じたのちも「自分が知ら
ない情報、自分が習熟していない技術」をうまく習得することができない。対話的、双方向的コミュニケーションの仕方が分からないからである。
彼らは長い時間人の話を注意深く聞くことができない。人にものを教わるときの適切な儀礼(表面的な恭順さの演技)ができない。なによりも、教える相手に
「自分が何を理解していないか」を理解させることができない。この子どもたちが「学級崩壊」の主人公たちである。
要するに、彼らは「自分が知らないこと、自分に出来ないこと」をどうやって知ったり、できたりするようになるのかの「みちすじ」が分からないのである。
だから彼らには「自分がすでに知っていること、自分がすでに出来ること」を量的に増大させる道しか残されていない。
彼らは、小学生のままの幼児的で自己中心的な自我のフレームワークの中に、TVや音楽やファッショソや...トリヴィアルな情報をぎっしり詰め込むことを
「情報の摂取」だと錯覚したまま成長する。..このような子どもたちはもちろん大学でも何ひとっ学ぶことができない。
(以下略)
---------------
物理学は越境する ーゲノムへの道ー 和田昭允
よくあることですが、相手に負けない議論となってしまって、論理の筋道など
どこかにスッ飛んでしまう。さらにひどくなると、身分や権威を笠に着て相手を
理不尽に威圧する。若い人は、後で何かしっぺ返しされそうで正論が言いにくくなる。
こんなことは科学や技術の社会では全く不毛、百害あって一理無しです。そうは言っても、
最近よく見られるいくつかの大企業凋落の原因をよく読むと、まだあることらしいですね。
でも、集団のモラルが崩れ出すと、もう個人では止められない。
私もこれまでいくつもの研究者集団の世話をしてきましたが、それが一番怖かった。
---寺田寅彦「春六題」1947
もしそれが成功して生命の物理的説明がついたらどうであろう。
科学というものを知らずに毛嫌いする人はそういう日をのろうかもしれない。
しかし生命の不思議がほんとうに味わわえるのはその日からであろう。生命の物理的な
説明とは生命を抹殺する事ではなくて、逆に「物質の中に瀰漫する生命」を発見する事で
なければならない。
物質と生命をただそのまま祭壇の上に並べ飾って賛美するのもいいかもしれない。それはちょうど
人生の表層に浮き上がった現象をそのまま遠くからながめて甘く美しいロマンスに酔おうとする
ようなものである。
これから先の多くの人間がそれに満足するものであろうか。
私は生命の物質的説明という事からほんとうの宗教もほんとうの芸術もうまれて来なければ
ならないような気がする。ほんとうの神秘を見つけるにはあらゆる贋物を廃棄しなくてはならない
という気がする。
---寺田寅彦1948
科学の進歩を妨げるものは素人の無理解ではなくて、いつでも科学者自身の科学そのものの使命と
本質とに対する認識の不足である。深くかんがえみなければならない。
-----中西重忠 「未知」の怖さを知り,正確さ保て
研究論文というものは、科学者が自己を表現できる唯一の機会である。その質はもちろん正確さが厳しく問われるべきだ。1回でも大きなミスをしたら、その後
の論文をだれが信用してくれるだろうか。意図的でない誤りならば許してやろう、ということは絶対にない。
我々は事実を知り得ても、それが真実であるかどうかは、本当のところはよくわからない。そのためにあらゆる方向から、それが真実であることを示す必要があ
る。データを都合の良い論理に合わせてしまうのが,誤りや不正事件が起こる根源ではないかと私は思う。
私は、大学院生に論文を書かせるとき「これが間違つていたら、科学者として生き残れないよ」と言い聞かせてきた。論文を書くことの責任を痛感させるその一
方で、その論文のすべての責任は、研究室のボスにあると考えている。出てきた成果を絶えずいろいろな方向から見て、正確さを保たなければならない。
生データを必ずチェツクする,共同研究の場合には相手の研究室に出かけて私たちが実験することが必須である。定説を書き換える
ようなデータが出たら、別の人に同じ実験をさせて確かめることだつてある。
研究というのは誰もやっていないことに挑むのだから、どういう落とし穴があるかわからない。たとえば,「薬品や試料は使い切ってはいけない」という心がけ
は、教科書などには書いていない。再実験をする時、同じ実験条件をそろえるためには絶対に必要だ。
研究を行うことの意味や研究の怖さを、常に後輩に教えていかくてはならない。
---------------朝日新聞2006年3月11日「科学論文不正なぜ続出」
早く論文を発表したい研究者と話題性のある論文を掲載したい雑誌の思惑が一致。
有名誌に載った論文数が,研究機関での地位や資金の獲得に直接結びつく。
--------------------------------------------------------
* 日経サイエンス2006年11月号pp.46-54 P.E. ロス The Expert Mind
チェス,クラシック音楽,サッカーなど様々な分野において,「厳しい訓練」は上達を得るためのカギとなっている。
最近の研究で,上達にとって重要なのは,持って生まれた能力よりも動機づけであることが示されている。.......
重要なのは経験そのものではなく,「努力を要する訓練」,すなわちその人の能力をわずかに超えたところでチャレンジを繰り返すことが必要であ
る。.......
生まれつきの才能を重視する考え方は,達人やスポーツの指導者の間では根強い。だが,不思議なことにそれを裏付ける証拠はない。....
スポーツや音楽をはじめ,様々な分野の教師たちは,才能が重要だと信じる傾向にあり,見れば才能の有無が判断できると考えている。しかし,実際には,教師
は能力と早熟を混同しているようだ。
---------------------------------------------------
文系就職考
理系から技術者になっても日の目!?をみないし,
それならいっそ文系就職できたら外資をと考える学生が多い。某有名T大学工学部では
大学院に進むよりは外資という優秀!?な学生が実際多いらしい。
(研究のおもしろさを味わう前に,巷の情報に踊らされているように
思ったりもするが...)
また,文系の友達に言わすと,お金儲け・会社経営は
マネージメントがすべてなんで理系の人間出る幕は少ないとのことらしい。
しかし,マネージメントというが
売るべき物を作れない・持たない組織になればなにをマネージメントするのか?
実際,半導体を生業としている商社の友達は工学部の没落!?を嘆いている。
そしたら過去に文系就職した人はどう考えているのかということを
調べてみると以下の文章が見つかった。ようするに甘い話はないということなのか?
文系就職を考えている皆さまどう考える?
「追記 08Oct」
サブプライム問題で,いわゆる大恐慌がおこりつつある今,
ゴールドマンサックスをはじめ外資金融系に文系就職された皆さんお元気で
おすごしですか?
>>>
就職先選定のアドバイス-就活メガバンク編 ビーシープロダクツの社長ブログより
2006.11.25 http://bcp.moe-nifty.com/products/2006/11/post_64e7.html
採用活動が始まったので、今後順次機会を設け、大学生就職先選定のアドバイスをしていきます。まず、傾向として、今年の大学生は大手志向がより強く、より強い安定志向が出ます。学生の多くは、大手の企業で、専門知識を積み、キャリアを踏んで独立やベンチャー系に転職する希望を抱きます。そういった中、近年人気上位ランクから外れていた「メガバンク」が今年は相当上位に現れるでしょう。まず、この銀行業界について、理系学生に対してアドバイスがしたいと思います。
私自身は世間で言う理系の出身です。本来文系と理系の分類の価値はないと考えますが、敢て定義しますと、理系は言葉よりイメージでモノを考える傾向を持つ人間で卒業まで一生懸命学業に頑張った学生と思います。銀行業界においては文系中心の世界で、その折角頑張った理系の知識は生かされる場面が少ないのです。ファイナンシャルの道を目指す場合、数学が理論中心であり、生かされる面もありますが、通常業務は文系が優位な言葉の能力勝負で出世が左右されているようです。
そのような環境下、今年は金融システム構築のため、内部監査強化もあり理系学生の大量採用を進めています。システムの採用を強化のため、理系学生に対して本来能力の分にあわない高給を準備し、呼び込みをしています。しかし、重要なことですが、銀行にはシステムの学生を育てきる環境がないと思います。まず、古参の上司は理系技能を評価出来ないのです。次に、バブル期に採用された理系学生だった方々は、文系技能を評価され、苦しい思いをしました。そして、最近までシステムを全て外注化で進めたため、大量の理系人間を放逐しています。
現在、金融システムを新規構築することになったため、再度大量に慌てて中途採用をして内部監査強化を進めて居ます。このように、銀行では技術に対する視点が短いため、腰をすえた育成は難しいのです。理系学生が技術を生かせる環境や時間がありません。技術立国の視点を持つ会社を探してください。これから自分の将来手に付く仕事のことを考え就職先を見て欲しいと思います。
---------------------------------------------------
真のイカ京になるしかない!
---------------------------------------------------
身近な人しかみていないからかもしれないが,どうも
優等生が多いな。先生に言われたことそつなくこなすけど
イケテナイ・オモロナイ! むしろ,長いこと留年したり
してる人間がすごかったな。すぐに教員のレベルを自力で超えていったもんね。
それが,真のイカ京なんだろうね。
研究室によって人生が決まるような考え方がはびこっているけど,
それは受身すぎるように思う。
自分の寄与で研究室を変えたろぐらいの気概が欲しいね。
で,すべての工化生に一言
"Don't smile so much, it can make you blind."
「あまりヘラヘラするなよ。メクラになっちまうぜ。」
Stranglers (Punk Rock Band), ジャン・ジャック・バーネル
( "Something Better Change"3回連続演奏は、特に重要なエピソードだ。初来日時、彼らは熱狂的に迎えられたが、彼らは何故か"Something Better Change"を連続で演奏したのだ。しかし観客は怒る様子もなく嬉しそうにノッている。3回目でヒューはキレて怒鳴り始めた。日本のファンは何がなんだかわからなかった。彼らのメッセージが理解できなかったのだ。その時言ったJJの言葉はしばしファンの語り草となった。"Don't smile so much,it can make you blind.(あまりヘラヘラするなよ。メクラになっちまうぜ。)"http://homepage1.nifty.com/earlinblack/sakusaku/1_1.htm より)
ちなみに,Stranglersは京大西部講堂にも来てます。
見にいけなかったのは残念!(自転車部のStranglers命の先輩はいったそうです)
西部講堂といえば,私もたまたま参加できたPoliceのライブのことを
書いてくれているサイトがありました。感謝。
http://ameblo.jp/okami55/entry-10016843095.html
Policeのライブが本当にあったのかどうかを疑っている人は,
PoliceのDVD "Live Aroud The World"に西部講堂での映像(1980年2月20日)
のライブ映像あるらしい。1回生の自分が映っているかも。
で,ありました。
Police at 西部講堂1
Police at 西部講堂2
PoliceはStranglersに西部講堂でのライブをすすめられたらしい。
StranglersのライブもPoliceのライブと同じく伝説のライブだったらしく,
自転車部先輩から,西部講堂の前の広場が
バイクと革ジャンの連中でいっぱいになったとか聞いた。
Oxford, UKのCD屋でStranglersのCDを買おうとおもってながめていたら,
現地の革ジャン着たニーちゃんにおもいっきりガン飛ばされた。
----Stranglers伝説(Netの書き込みから転載・ご容赦を)
ジャンジャックは初来日のライブのとき
皮ジャンにナチ鉤十字マークつけたバカに
ステージからダイブして殴りかかってた。
来日した時、レストランに連れていかれたストラングラーズは
値段の高さに不満を言い、駅の立ち食いカレーで済ませた。
金を払うのはストラングラーズではなにのに。
ジャン・ジャック、スーパーのビニール袋にTシャツを何枚か
入れただけで来日していた。
---------------------------------------------------
WW II
---------------------------------------------------
深夜のNHKで,WW IIの経験者のインタビューが流れている。
沖縄戦を戦った山形のおじいちゃんが,
戦友が部下が死んでいくといきに
だれ一人として「天皇陛下万歳」とか「お母さん」と言ってなかった,
全員が軍上層部批判をしながら死んでいったというのは驚いた。
また,武器弾薬や食料の補給もなしで戦えっていうのは
なんて杜撰な戦略を軍上層部は立てたのかと鋭く言い切っていた。
---------------------------------
南米チリを出発しアタカマ砂漠を横断、アンデス山脈を越える1000キロの旅に成功した
リヤカーマン永瀬忠志氏の言葉
安全なところって楽しくない。先が見えちゃうんです。危険なところって、先が見えずに不安になる。でも思わぬものに出会ったり、思わぬことが起きると『やっぱり来て良かった』と思うんです」
アンデス山脈の道中では高山病に。寝ている時に気分が悪くなり、テントを開け何度も吐いた。昼間は30〜50歩ほど歩き1度休憩を入れ、息を整える。その間にも、吐き気は襲ってくる。1日に1キロしか進めなかったこともあった。「もう駄目だ」と思う時に、思い浮かぶのが家族の姿だ。
「母親が『大丈夫だから、見てるからね』と語りかけてくる。子供が道の前に立っているような気がする。『お父さんが来た』と走って駆け寄ってくるんです」
幻覚を見るような苦しい旅。しかし、そこには大自然が広がり、現地の人との温かい触れあいがある。薄緑のきれいな水をたたえた湖にピンクのフラミンゴが降り立つ。それは「夢の世界、幻想の世界」。そして最大の楽しみは「お風呂上がりの一杯のような感じ」で、日が暮れるころに飲む缶ビールだ。
「途中でやめていたら、今はなかったなあという時がある。人との出会いであったり、アンデスのようなきれいな自然を見たりすると『よーしまた歩いていくぞ』となる。やめたい帰りたいと思っている時間が99%だとすると、来てよかったなあと思うのは1%。でも、その1%が大きいんです」
----------------------------------
内田樹氏(神戸女学院大)のブログより
知性の総量というのは世代によって変わるものではなく、その世代ごとに対象を変えるだけである、という村上春樹さんの知性説に私は同意するものである。
今の日本社会では「知性的にならない」ことに若者たちは知的エネルギーを集中している。
無知は情報の欠如のことではなく、(放っておくと入ってきてしまう)情報を網羅的に排除する間断なき努力の成果である。
「知性的になってはならない」という努力を80年代から日本は国策として遂行してきたわけであるから、これはスペクタキュラーな「成功」なのである。
だから、私たちが学生に与えるべきなのは知識や情報ではなく、「知性的な人間になっても決してそれで罰を受けることはないんだよ」という保証の言葉なのである。
--------------------
北京オリンピックで団体4位に入った卓球女子「平野」選手がおもしろい。
あれだけガンを飛ばすのをみて昔のスケバ*を思い出した。
平野早矢香は断じて「鬼」ではない。
”やる”か”やられるか”の世界に住む
現代の侍(さむらい)である。
失うことから全ては始まる
正気にては大業成らず
鬼より
-----------------------
「賃金低い、出世しない」 「工学部離れ」で志願者4割減
大学工学部の志願者が、ここ5年で4割も減少している。この「理系離れ」について、専門家は、工学部出身者が会社内で不遇なことも一因とみる。金融・証券の会社に就職する例も増え、このままでは、技術立国ニッポンは沈没するのか。
文系・理系の生涯賃金格差が5000万円
「エンジニアが下積みになっています。親や先輩、友人の父親を見て、生涯賃金のことが分かるので、インセンティブが小さいんですよ」
「理系の経営学」などの著書がある東大大学院工学系研究科の宮田秀明教授は、理系離れと言われる現状をこう嘆く。
理系、特に工学部離れは、確かに顕著なようだ。文部科学省の学校基本調査によると、2008年度入学の大学入試で、工学部の志願者数は、前年度比 1割近く減の24万人余。これが5年前に比べると、なんと4割も減っているのだ。予備校の調査では、ここ1、2年は学校側の対策もあってやや持ち直しているという。しかし、ピークだった1992年からの下落傾向に歯止めがかかったとまでは言えないようだ。
工学部離れの理由について、宮田教授は、高度な技術が要求されるにもかかわらず、エンジニアの賃金が安く、幹部に出世しにくいことを挙げる。
「今はプログラミングやITの知識が要求されるなど、昔より守備範囲が広く技術が難しくなっています。きちんと学ぼうとすれば、医学部のように 6年かかります。しかし、難しいことをしても、それに比例した見返りがありません。日本では、マイクロソフトのビル・ゲイツのような成功例が出てこない。理系離れは、好き嫌い、モチベーションより、構造的な問題ですね」
低賃金については、衝撃的なデータがある。日経ビジネスの8月25日付サイト記事によると、大阪大大学院の松繁寿和教授は、文系・理系両出身者の生涯賃金格差が5000万円という10年前の調査が、今も当てはまることが再調査で分かった、と言うのだ。特に、文系が多い金融・商社と理系が多い製造業の間にある産業格差が、そのまま賃金格差に表れたという。また、理系出身者の方が課長になるのが遅いなどの昇進格差も関係しているとしている。
東大工学部から金融・証券就職が激増
工学部のうち、特に、電気・電子系の人気が落ちているようだ。
学校基本調査によると、2008年度入試で、電気通信学部の志願者数は、5年前より5%減の3968人。日経ビジネスの08年8月19日付サイト記事では、東大工学部の3年次における進学振り分けで、電気・電子系が5年連続で「底割れ」したと伝えている。07年度の進振りでは、電気・電子系3コースのうち2コースで定員に達しなかったというのだ。
その背景として、半導体やディスプレーの開発で韓国に遅れを取るなど、電気系産業の厳しい状況が挙げられている。前出の宮田教授は、「(株価暴落の)ソニーショックで始まりました。情報システム系もそうですが、仕事がきついのに給料が安く企業に魅力がないのが原因でしょう」と分析する。
とはいえ、電気・電子系の技術は、自動車産業や重工業でも必要とされるようになっている。「車は今や、コンピューターのようなものだからです。重工業でも、飛行機の開発が始まっています」と宮田教授。
ところが、新技術開発を担う大学院でも、志願者が減っているというのだ。日経ビジネスの8月26日付サイト記事によると、京大工学部では、博士課程の定員 200人に、京大生は120人ほどしか集まらず、留学生を入れて埋めているという。その背景に、経済的なメリットが少ないことがあるとしている。
宮田教授によると、こうした状況があって、東大でも工学部から金融・証券の会社に就職する学生が増えている。「私の研究室でも、10年以上前は20〜30%に過ぎなかったのが、今や100%にもなるんですよ」。
「まず、産業界を改革しないといけません。そうしないと、賃金がすぐ倍になる外資系に、いい人材が行ってしまいます」と宮田教授。さらに、船舶工学系の4 専攻を改編して東大でシステム創成学科を立ち上げた経験から、「時代に合わせて、大学も会社と同じように変わらなければいけません」と話している。
http://www.j-cast.com/2008/08/30025916.html より
-------------
面従腹背(めんじゅうふくはい:表面上は従うように装うが、内心は反抗すること。)
面従腹背はある意味、社会人の生きる知恵だが,
Teacher 「****ちゃうんか? △△△△をやっておかなあかんわな。」
Student 「はい,わかりました。やっときます。」
数日後,Teacher 「前言ってたあれどうなった?」
Student 「ハァー??」もしくは「苦笑い」もしくは「沈黙」。
めんじゅうふくはい,お互いに不幸なり!
-------------------
京大西部講堂にも来たらしいFrank Zappa 語録
Some scientists claim that hydrogen, because it is so plentiful,
is the basic building block of the universe.
I dispute that. I say there is more stupidity than hydrogen,
and that is the basic building block of the universe. -- Frank Zappa.
科学者は宇宙は水素でできているっていうんだ、宇宙には水素がたくさんあるからね。
でもオレは違うと思うよ。水素よりもバカのほうがもっと多い。
宇宙はバカでできていると思うんだ。(フランク・ザッパ)
----------------------------------
2回生の授業
今,2回生相手に分析化学1なんての冗談も授業中に言わず教えている。ものすごく
出席率は高い。出席を取っているからか? しかし,いつも出席表をまわす時に後ろめたい。
なぜか?
自分が2回生の時は専門の授業はほとんどなく,語学と体育+αにしか行ってなかった。
語学と体育は確かに出席をとっていたがそれ以外はなかったようにおもう。
皆さん人生で最大に遊んでいたわけです。
勉強にたいするモチベーションは逆に人生で最低だったね。
今でもおぼえているが,
物理3という科目(量子力学)の試験で,Schr\"{o}dinger方程式を書けという問題が
あった。その後にその方程式を解くという問題だったとおもう。当然ながら,1回も授業に
でておらず,ノートもなし,教科書も買ってないので,(試験に行くこと自体意味がなかった
んだろうけども,何か期待することもあったりしたので。。。笑)まったくの白紙で速攻試験場を
後に,完全なゼロ点であったわけ。
ってここまではよくある話。しかし,ここからが自分でも驚き!
人生わからないもので,今はこのSchr\"{o}dinger方程式
の数値解で飯を食っているんだから!どうしてそうなったのかは
M1の相転移!ってだけ言っておこう。えらそー!
だから,2回生にあれこれ説教がましいこと言うたびに自己反省をくりかえしてるってことです。
あのころのくそ生意気な自分が今2回生だったら,説教くさいバカオヤジぐらいにしか
おもってないだろうって。
で,教訓(オヤジ臭いが)
"Tell me and I forget,
teach me and I remember,
involve me and I learn."
[Benjamin Franklin]
“Tell me and I’ll forget;
show me and I may remember;
involve me and I’ll understand.”
[Chinese Proverb 孔子の言葉らしい?]
ぼーっと聞いてるだけは,すぐに忘れるし,
ちゃんと「教えてる」んだろうけど,せいぜい
(つかっている用語を)覚えてるぐらいかな。
自分の問題としてやってみれば,
理解できるんだろうけどね。
[山本訳]
------------------
濃度??
2,3年前に紀本さん(当時分析化学会近畿支部長)より
最近の若い子は濃度の概念がわからない子が多いという話を聞いた。
また,学生実験の現場でもそのように感じる経験が何度かあったのと
KITでの前田先生の経験も直前に聞いていたので,
試しに工学部工業化学科基礎化学コースの2回生にレポートで濃度の問題を問うた。
1) 重量% w/w%,重量モル濃度,容量モル濃度の
定義をきっちりする必要があったのと,濃度の感覚をつかんでもらうために
食塩水を例に挙げ(海水,生理食塩水,味噌汁当のスープの塩分)授業で20分以上説明した。
「しょうないことを教えるな!」との気持を学生さんはもつだろうな!思いながら。
2)説明後,濃塩酸37 w/w%の重量モル濃度,容量モル濃度への換算をレポート課題とした。その際,
溶液の密度,HClの分子量も与えている。
3)翌週,出席者60名弱でレポート提出者20名,そのうち正解者 12 Mは7名であった。レポートを出さないものが多いことにも驚いたが,正解者が半分以下なのには唖然というか大ショック。
分析化学の滴定曲線や緩衝強度とか教えてる場合じゃないと。ましてや,統計力学,量子力学なんて。。と絶望的な気持ちに。
4)塩酸の場合の解答を,丁寧に授業で解説し,その後
しつこく濃硝酸の重量%からの濃度の換算を再びレポートに。分子量,密度も与えているが,
念には念をいれて,答えは16 Mになるからとも解答も教える。
当然,正解率100%に近づくことを期待している。
5) 次の週のレポート結果は,35名正解,6名不正解。2名未回答。35/43 = 81 %の正解率。
解答も教えたのに。もう笑えなくなった。
院生の皆に聞くと,”ゆとり”世代かもと。
大学入試というより高校入試の範疇なのだとか。
有名私立中学入試ではではもっとむずかしい濃度の計算が問題としてでてるらしいが。
また,ある院生氏曰く。
「そういえば,4回生のS君も試薬調製の際に電子天秤の前でやけに長いこと計算してましたよ!?。
なんであんなに時間がかかるかなと思っていたんですよ」と。。。ええっ!
大丈夫なんかな???
濃度の計算を100倍間違えたおかげでノーベル賞につながった場合もあったようだけど???
-------------------
装置自作の薦め
「真のオリジナルな実験をするには,装置を購入するんではなく
自作しないといけないんだよね。」とN先生に昔いわれた。理学部の伝統らしい。
というよりは装置購入ができなかった。毎日工具をつかってごりごりと。
楽しかったけど現代の意味での成果はでないよね。
で,桂に桂ものづくり工房ができた。その研修を学生さんと受けてきた。
桂ものづくり工房には,
旋盤,フライス盤,帯のこ,ボール盤,回転砥石等がありまして,
研修は機械系の職員さんによる説明,参加者の実習も伴ったもので
大変有意義なものでした。(京大で一番意味のある授業・研修だったようにおもいます)
工房は,ちょっと行って直ぐに使わせてくれるように使い勝手も工夫していただいてます。
工房の設立には当然ながら大反対があったようですが,
前工学研究科長のN本先生が裁量経費でおしきったようです。
研修をうける人も,若い方を中心に100名以上(予想に反して)となり,
工房が全く盛り上がらないというのは杞憂に終わったようで。
おもしろい流れも芽生えてきたのでしょうか?
ーーーーー装置等の自作については,以下のような話があります。ーー
The Cavendish Laboratory (Cambridge Univ., UK)
has traditionally worked on the 'do-it-yourself' principle
working with one's own hands to build a
large part of the equipment used. It is fortunately set in an
intensely stimulating intellectual environment, and it is fed by
a stream of very gifted research students from the Cambridge
Colleges and from the Universities of the world. These factors,
together with its inspired leadership, have been responsible for
its success. SIR JOHN COGKCROFT O.M., F.R.S.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
08/Oct/21 ーーーーーーーーーー池田峰夫先生ーーーーーーーーーーーーー
本日吉田で「京大夢ノート」なる本をもらいまして
(朝8時のキャンパスで笑顔をふりまき走ってきたかわいい女の子がくれたもんで。。。)
ついついうけとってしまいました。
結構おもしろい記事が載ってまして,
工学部の4回生のとき(土木学科向けの)工業数学Bをおしえてもらって池田峰夫先生
(なぜか南部陽一郎氏の対談でも名前がでてたので素粒子論やってはった!?
そんなそぶりはみせはらへん温和そうな先生でした。若くして亡くなれれたのが残念。
先生の著作「応用数学の基礎」は垣内研のバイブル!)
の座右の銘は
「学問は,一升瓶を枕にやる」もんだとおしゃっていたそうです。
今、こんなすばらいことを言ってくれる先生は、京大でお二人だけしかしらないな。
H先生とK先生。
-------------------- ご臨終メディア(集英社新書,2005) 森達也・森巣博 著
森巣:
フランツ・ファノンが言うように、「無知」というのは知識がないことではない。そんな
ことを言えば人は誰でも皆ほんんどの局面では無知なのですから。そうじゃなくて
無知とは、「疑問を発せられない」状態を指す。
。。。
森:
全体主義とは、構造的には無自覚な萎縮・保身の継続的な集積です。
----------------------山本義隆 ”熱学思想の史的展開”
物理や数学などの分野が毛嫌いされている。
必要性をまったく感じないからだということに根ざしている。
積み上げをしないといけないので”しんどい”ということはよくわかる。
化学の分野でも,物理化学というのがあり
やはり有機化学や生化学を目指す学生さんには”目障り”でしかないらしい。
4月から物理化学の授業をするので,バックグラウンドを押さえておきたいと思い
山本義隆氏の”熱学思想の史的展開”(筑摩学芸文庫3冊・全改訂をされたということで買い直した。)
と朝永振一郎氏の”物理学とは何だろうか”を購入。
山本氏の本の第1巻はかなりおいかけるのがしんどいが,衝撃的な文章が。
今手元に本がないので,(引っ越しの段ボールの中)正確にはかけないが,
”熱力学の定量化(要するに数学ですね。ここがわからずに物理化学は毛嫌いさせるんです。)
を推し進めたのは,いわゆる高踏的な動機(真理の探究?)からではなく,
商業主義に基づいた実践(すなわち金儲け)からの要請である。”と。
今や,サブプライムローン問題でつぶれかけているが,
ちょっと前まで某国での儲けといえば数学や物理を用いた金融工学であった。
倫理観の欠如の問題のみが指摘されているが,
同様な運用による”お金もうけ”は
伊藤の”確率論”を読めない日本の学卒生にはできそうにもない。
有名国立大の理系でも一部の分野においては,ほとんど数学は出来ないということ。
(センターと2次試験で入試科目にあるにも関わらず。)
どうしてこのようになったのは某国による陰謀説であるとさえいう人さえいるが,
”数学や物理”を毛嫌いする
理系の学生が”文系”就職してもと思うのは私だけだろうか?
----------和田秀樹氏 エリートの創造(阪急コミュニケーションズ)
「現代の教育心理学の考え方では、”外発的動機づけ(入学したらバラ色の人生保障される?:山本註)から
内発的動機づけ(研究おもしろいやん:山本註)に内化されるプロセス”が重視されるという。」
これってまさに大学の使命だと思いますが。。。あるいは、上で書いたM1の相転移もそうかもしれません。
「金の力でエリートを動機づけするのは危険極まりない。1)金の競争では米国にかてない。(日本のプロ野球がMLBに食われた。)2)貧富の差の拡大は、めぐりめぐって自分の首を絞めることになる。3)モラルハザード 4)世間の目の抑止力がなくなる。5)治安の悪化」
「文科系の学部出身者で入試の際に数学を選択したものとしないものでは、年収に107万円の差(共通一次試験以降)
(京大西村和雄教授の調査)」
----------------------------------
Adios and Good luck!
KU guys.
----------------------- 京大アメフトHPの水野彌一監督のおことば(http://www.gangsters-web.com/team/index.html)
アメフト部員向けに書いておられるんでしょうが、今の自分にとても響きます。!!
スポーツで強いチームを作る王道は、条件を整える事。
それは優れた選手を集め、環境を整え、コーチングスタッフを充実させることである。
しかし国立大学である京都大学では、私立大学と同じような条件整備はほぼ不可能である。我々の場合は、大学からの物理的支援は練習のためにグラウンドを使わせてもらえるだけである。あとは全て自助努力によるので、全ての条件は決定的に劣っている。その中でも、人材面において望んだ選手を入学させることが全く不可能である、という条件は、求める人材を推薦制度等によって数多く入学させることができる私学との大きな差である。
このような状況は昔もそうであったし、今も変わる所はない。その中で日本最多の4度の全日本一を勝ち取ったのは、人間その気になれば不可能と思われる事も可能になるという事の証左である。
アメリカンフットボールは個人競技ではなくチームスポーツである。技術のウェイトが比較的少ない格闘技である。さらには攻守交替制であるため、戦術が重要であることなども、他スポーツより京大に有利であるだろう。しかしそんな事は決定的な要因ではない。最も大切なのは、やる気なのである。だが、元々困難で厳しい挑戦であるから、それでもやる気になるというのは容易なことではない。肉体的な強さは人によって差があるように、精神・意志の強さにも違いがあるから誰もができる事ではない。
京大生の場合、入学時と比べて体重は1.3倍、筋力は3倍成長するというのは普通であるが、技術はそれ以上に向上する。さらには、精神的な成長は比較にならない。練習によって肉体を鍛え、技術を身に付ける以上に心を強くするのである。
我々は、アメリカンフットボールを楽しめと常々考えている。しかしここで勘違いしてはいけないのは、スポーツを楽しむということと、楽しくスポーツをするということとは全く意味が違うということである。本当に楽しいのはレベルの高いプレーをする事である。そのためには上達する事が大切である。そのためには効率的なやり方が重要となる。しかし初心者にはそれは分からない。やりたいようにやっていたのでは上達は望めない。そこで重要なのが基本である。基本は長い間に培われた、優れた方法論である。だが、技というのはできて初めてわかるものである。繰り返し練習すると体が勝手にやってくれるようになる。そうなると意識を外に向けて行動できるようになる。初めて基本が生きてくるのである。そうすると今までと別次元のプレーができる。そこまでくると自分というものが見えてくる。自主的にやれるようになる。もっと上達したいからより一層練習する、上達するからより一層やる。エスカレートしやめられなくなる。熱中するとかのめり込むというのはこの事で、こうなるとしんどくても辛くても関係ない。本当に楽しい事である。
こうしてやっていてもやがて壁にぶつかる。やってもやっても上手くならない。一方勝つために自分は上達しなければならない。これは大変辛いことである。今この国では良いイメージを持って前向きにチャレンジしようが主流である。しかし志が高ければ高いほど困難も大きいから、成功の見込みの少ないチャレンジはバカのする事というのである。これでは高い志は果たせない。その厳しさに耐えて挑戦し続けなければならない。これは逃げ出したくなる自分との闘いである。この闘いに勝つのは大変難しい。しかし、闘い切る事によって、自分は自分に負けなかったという自信が生まれる。自分には負けないという自信、これがあるから基本的に楽観主義になれるのである。困難な時、厳しい時こそ前向きになることが成功の最大の秘訣ではないだろうか。こんなに価値あるものはない。また、どうすれば壁を破れるかわからなくても、ある時「あ、そうか、これだったんだ」という気付きがあるものである。その時壁は消え、新しい自分、新しい世界がある。よしんばある時点では壁を破れなくても、自分の限界を知ることができる。そうするとその自分をそれなりに生かす知恵が生まれる。より一層向上する意志が生まれる。そのようなありのままの自分を知る成長を通して、謙虚であることの大切さを学ぶことができるのである。
このように自己探求と同時に、チームスポーツの勝利はチームの勝利であることを忘れてはならない。選手は全員チームの勝利に貢献しなければならない。フォアザチーム、チームのために何ができるか、自分をどう生かすか。
貢献の仕方は皆違う。エースQB、オフェンスライン、基本習得中で強い相手との対戦にはまだ出られない者、さらにはマネージャーやトレーナー、監督もコーチも全員がチームの勝利のために存在するわけである。フィールドでは全員が自分の役割を果たす、あいつならやってくれる、あいつは逃げないという信頼があるから、自分のプレーに専念できる。そういう仲間と共にチームの勝利という共通の目標のために共同して努力をすることを通し、真の信頼を築く。このような仲間は一生の財産である。
この他にも学ぶことは数多くあるが、勝つ事を追求して自分というものが見える。そして自分を生かす知恵と自分に負けない自信を得る。これが学生スポーツの最大の意義であろう。
たかがスポーツ、されどスポーツである。
----------------------------------------
理解の五段階レベル:オリジナルアイデア 宇治原エネ研・湯塩先輩
1 何の事をいっているのかさっぱりわからない。
2 「言葉」はどこかで聞いたことがある。
3 どの本どの文献に書いているあるのかを指摘できる。
4 本や文献をみながら(他人の論理で)他人に説明する事ができる。
5 その場で黒板等をつかいながら(自分の考え方で,できたら複数の方法で)他人に説明することができる。
わかってるつもりでも大概のことは、3,4以下かもしれません。
------------------------------------------